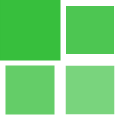病室で気づいたこと――医師から家族になって見えた風景
鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。
私が医師になって、もう40年近くになる。専門は、最初は内科の内分泌代謝だった。その後、地域医療、総合診療へと移ってきた。いま振り返ると、臨床だけでなく、基礎研究やフィールド調査、大学での教育など、ずいぶんいろいろな仕事をしてきたと思う。
最近は教授という立場で地域医療学講座を預かって、15年が過ぎた。地域医療学を担当するようになってからは、学生教育が仕事の中心になったが、外勤先での外来や、大学病院の総合診療外来は続けていた。ただ、入院患者を主に診る仕事からは、しばらく離れていた。
今回、ある事情で家族が入院することになった。病室にいる時間が増え、医師としてではなく、患者の家族として医療者の仕事ぶりを見ることになった。そこで、これまで気づかなかったことが、いくつも見えてきた。
家族が入院して、まず頭に浮かぶのは、不安である。これから何が行われるのか。どんな治療なのか。痛みはどうなのか。いつ退院できるのか。そもそも退院できるのか。考え出すと、「?」はいくらでも出てくる。
不安が強いと、医師の言葉だけでなく、表情や雰囲気、ちょっとした仕草までが気になってくる。「この治療を1か月ほど行います。検査もしますが、まず心配いりません」と言われても、医師の顔に一瞬でも陰りがあると、「何かあるのではないか」と勝手に想像してしまう。不安が強いほど、言葉は深読みされる。
家族が入院して、もう一つ、はっきりわかったことがある。入院生活の日常を支えているのは、ほとんどが看護師さんだということだ。
食事、排泄、検査の介助、痛み止めの調整。入院中の楽しみは三度の食事くらいだ、というのは本当だと思う。吐き気で食べられない日もあるが、少し良くなると、次の食事を待ち遠しそうにしている。痛みのことも、看護師さんはよく聞いてくれる。どこが、どんな動きで、どれくらいつらいのか。トイレに行くのをためらっている気持ちも、案外よくわかってくれている。
一方で、病状をあまり知らない技師さんが、ポータブル撮影の際に少し乱暴に身体を動かしたことがあった。そのあと数日間、家族の痛みは強くなり苦しんだ。医師の立場で病棟を回っているときには、なかなか想像できなかったことだ。
患者は、こうした細かな不安やつらさを抱えながら、病室で過ごしている。患者家族の立場から見ると、その日常を具体的に支えているのは、やはり看護師さんなのだと、腑に落ちた。
もちろん、主治医の先生は毎日病室に来てくれる。検査結果や今後の方針を説明してくれるし、痛みの専門チームが関わってくれたことで、薬の工夫もあり、本人はかなり楽になったようだった。ほんの少しの知識や工夫で、患者や家族の気持ちは、ずいぶん違ってくる。
それでも、どうしようもない痛みや、食欲不振、便秘など、本人にしかわからない苦痛は残る。それは、ベッド上での表情や、言葉の調子に現れる。どうしようもないこともある。回復するまで、耐えるしかない。
何もできない。それでも、そばにいる。
これは家庭医療でよく使われる「Being there」という言葉だ。「ただ、そこにいる」という意味である。頭では知っていたが、実際に家族のそばに座っていると、この言葉の重さを考えさせられる。
トルストイの『イワン・イリイチの死』では、主人公が最後に頼りにするのは、家族ではなく、無口な使用人だった。彼は多くを語らず、「痛いのですね」と繰り返す。それが救いになる。悲しみや嘆きは、必ずしも役に立たない。ただ、共感し、そばにいることが救いになる。でも、その役割を担う側のしんどさも、決して小さくない。
病室には、本当にいろいろな人がやってくる。食事を運ぶ人、掃除をする人、看護師さん、薬剤師さん、リハビリの先生、緩和ケアチーム。愛想のよい人もいれば、無口な人もいる。冷たく見えるが、実はよく気がつく人もいる。
ノックの音、カーテンが開く音。まず顔を見る。目線が合う人も、合わない人もいる。それでも仕事を終えて部屋を出ていく。その背中を見ながら、「ありがたいなあ」と思うことが多い。
私は医師として、これまで多くの入院患者を診てきた。病室に行くときは、いつも目的があった。診察、説明、指示。しかし、患者側から見える風景は、まったく違う。
医師の言葉や表情は、それほどまでに気になるものなのだ。だからこそ、医師が穏やかな顔でいることは、大事なのだと思う。
文化人類学には、参与観察という方法がある。現場に入り、その人たちとともに過ごし、内側の論理を理解しようとする。医療の現場も、外から見るのと、中にいるのとでは、見え方が違う。医師の世界を、患者の目線で見直してみると、ずいぶん違った風景が立ち上がってくる。
今回、病室に家族としていることで、同じ病室がまったく違って見えた。患者が何を心配し、何を求め、どんな言葉を待っているのか。医師の立場では見えにくかったことが、少し見えた気がしている。
黒澤明の映画『赤ひげ』には、忘れられない場面がある。赤ひげが若い医師に、「今夜亡くなるかもしれない患者のそばにいろ」と命じる場面。もう一つは、心を閉ざした少女の前に座り、何も言わず、おかゆを差し出し続ける場面だ。
映画だからできること、と思いながらも、自分ならどうするだろうかと考える。たぶん、簡単にはできない。すぐにあきらめるかもしれない。それでも、「そばにいること」の意味を考えずにはいられない。
病室で、特にすることもなく、家族の前にただ座っているとき、私はこの映画の場面を思い出す。そして「Being there」という言葉を、何度も頭の中で反芻するのである。
Author:谷口 晋一
こちらのページは、鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。